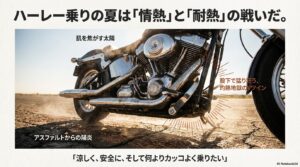ハーレーのアクセサリー電源の取り方を知りたい方に向けて、バイク電源の基礎から実践までをわかりやすく解説します。
バイクの電源を取り出す方法の全体像をはじめ、ヒューズボックスからの安全な取り出し方、USB電源を確保する際の最適な位置、そしてドライブレコーダーの電源をどこから取るべきかまでを整理しました。
さらに、電源取り出しハーネスの選び方や取り付け手順、M8ソフテイルのアクセサリー電源位置と接続方法にも詳しく触れています。
加えて、ダイナのアクセサリー電源の取り方、FXLRSソフテイルでの実践手順、ミルウォーキーエイトスポーツスターでの配線計画、ローライダーSTのACC電源対策、ウルトラでのACC電源活用法まで、主要モデル別の要点を網羅。
配線の安全性とトラブル防止に役立つ知識を、初心者にも理解しやすい構成でまとめています。
- モデル共通の電源取り出し原則と安全対策を理解できる
- ヒューズボックスやカプラーからの取り方を把握できる
- 主要モデル別の接続位置と手順の要点が分かる
- 失敗しにくい部品選びと施工の勘所を学べる
ハーレーのアクセサリー電源の取り方の基本と注意点
- バイクの電源を取り出す方法と仕組みを理解する
- ヒューズボックスの電源はどこから取り出せばいいか解説
- バイクのUSB電源はどこからとるのが安全か
- ドライブレコーダーの電源はどこから取ればいいのか
- 電源取り出しハーネスの選び方と取り付け手順
- M8ソフテイルのアクセサリー電源の位置と接続方法
バイクの電源を取り出す方法と仕組みを理解する

ハーレーに電装品を取り付ける際は、電源をどこからどのように取り出すかが安全性と安定動作の鍵となります。
特に、常時電源・ACC電源・イグニッション電源の3種類は、それぞれ異なる特性を持っており、用途や目的に応じて使い分けることが求められます。
常時電源は、キーオフ状態でも電力が供給される回路です。
時計やセキュリティアラーム、駐車監視機能を持つドライブレコーダーなど、エンジンを停止しても稼働させたい機器に適しています。
ただし、待機電流が常に流れるため、バッテリー上がりのリスクを考慮しなければなりません。
長期間乗車しない場合には、バッテリーターミナルを外すか、メンテナンス充電を行うと良いでしょう。
ACC電源とイグニッション電源は、キーオン時にのみ通電する仕組みです。
USB電源やナビ、ETCなど、走行時のみ動作させたい電装品にはACC電源を使うのが一般的です。
一方、点火系やECUなどと連動する電源を必要とする機器はイグニッション系に接続するのが適しています。
これらを正しく区別しないと、誤作動や電装品の故障につながるおそれがあります。
電源を取り出すポイントは複数存在し、バッテリー直結、ヒューズボックス、または車体側カプラー(診断カプラーやアクセサリーカプラー)などから選択可能です。
いずれの方法でも重要なのは、電装品の消費電流、使用する配線の太さ(例えば0.75sq~1.25sqが小型電装品では一般的)、ヒューズ容量、リレーの有無を一体的に設計することです。
これにより、焼損や誤作動、ノイズ干渉のリスクを最小限に抑えられます。
配線施工では、熱収縮チューブや自己融着テープで絶縁を強化し、タイラップで振動対策を徹底します。
金属エッジの干渉を避けるため、必ずフレームの内側や配線ホルダーを利用し、アース(マイナス線)は塗装を除去した確実な金属面に取りましょう。
アース不良は、通電不良や電子制御系のエラーを引き起こす原因になります。
電源種別と使い分けの目安
| 電源種別 | 主な用途 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 常時電源 | 時計、アラーム、駐車監視 | エンジン停止中も動作 | 待機電流の管理が必要 |
| ACC電源 | USB充電、ナビ、ETC | キーオンで自動起動 | 回路容量の確認が必須 |
| イグニッション | ECU関連、点火系連動 | 誤作動が起きにくい | 分岐は確実な方法で |
- 近年のハーレーはCAN通信(Controller Area Network)を採用しており、誤った場所から電源を取ると通信エラーや警告灯の点灯を招くことがあります。
- 配線を加工する前に、必ず車種専用のサービスマニュアルやメーカー公式資料で回路構成を確認することが推奨されます。
ヒューズボックスの電源はどこから取り出せばいいか解説

ヒューズボックスから電源を取り出す方法は、比較的安全かつ簡単にキーオン連動の電源を確保できる手段です。
特に、純正配線を加工せずに済む点が大きな利点といえます。
まず、テスターを用いてキーオンで通電し、キーオフで遮断される回路を特定します。
代表的には「アクセサリー(ACC)」や「イグニッション(IGN)」系統のヒューズが該当します。
ヒューズ電源取り出しホルダー(ミニ平型や低背タイプなど)を用いることで、純正ヒューズと交換する形で簡単に電源を分岐できます。
ただし、ヒューズ容量を超える負荷をかけないように注意が必要です。
増設側には必ず独立したヒューズを挿入し、電装品側の保護を確保します。
複数機器を接続する場合や、合計消費電流が3Aを超えるような場合には、リレーを併用して制御系と給電系を分ける構成が望ましいです。
制御信号をACCから取り、実際の電力供給をバッテリー直結にすることで、既存回路への負担を減らせます。
ヒューズを取り出す際は、装着方向にも注意します。
ホルダーの差し込み方向を誤ると、過電流時にヒューズが正しく切れず、保護機能が失われる危険があります。
作業前には、テスターで極性(+と−)を確認し、ホルダーの構造に合った方向で装着しましょう。
また、ヒューズボックス内は防水構造になっている場合が多いですが、追加配線を通すことでその密閉性が損なわれることがあります。
防水グロメットやシリコンシーラントで再封止を行うと、長期的な信頼性を保てます。
バイクのUSB電源はどこからとるのが安全か

USB電源をハーレーに設置する場合、ACC電源から取るのが最も扱いやすく、バッテリー上がりのリスクを避けられます。
USBポートの多くは5V・2A出力が標準で、スマートフォンの充電やナビアプリの利用に十分な電力を供給できます。
ただし、高出力デバイス(急速充電対応機器など)を同時に接続する際は、合計電流値が4Aを超えないよう確認することが大切です。
配線はなるべく短く、線径は0.75sq以上のものを選ぶと電圧降下を抑制できます。
長距離ツーリングで振動や高温にさらされる環境では、耐熱性・耐油性のある自動車用AV線(AVSやAVSS規格)を使用することで安全性が高まります。
配線経路はハンドル可動部に余裕を持たせ、断線を防ぐように取り回すのが基本です。
防水性能も重要なポイントです。
防水キャップ付きのUSBポートを選び、雨天時や洗車時に内部に水分が侵入しないようにしましょう。
特に、ハンドルバーやメーター周辺に設置する場合は、IP65以上の防水等級を持つ製品を選ぶと安心です。
また、低電圧カット機能付きのUSB電源ユニットを採用すると、バッテリー電圧が12Vを下回った際に自動的に出力を停止してくれるため、長時間停車中のバッテリー消耗を防げます。
常時電源からUSBを取る場合は、必ず物理スイッチを介すか、リレー制御を追加して手動で遮断できる構成にしましょう。
最後に、電源を取り出す位置や施工方法は、車種や年式によって異なる場合があります。
誤った接続は電子制御系統に影響を与える恐れがあるため、施工前にサービスマニュアルを確認し、純正アクセサリー用電源カプラーの有無を調べることをおすすめします。
ドライブレコーダーの電源はどこから取ればいいのか

ハーレーにドライブレコーダー(ドラレコ)を設置する際、最も重要になるのが「どの電源から取るか」です。
適切な電源選択を誤ると、バッテリー上がりやノイズ障害、さらには車両電子制御系への悪影響を招く可能性があります。
そのため、構造的な理解と正しい施工手順が不可欠です。
一般的に、ドラレコはエンジン始動と同時に録画を開始できるACC電源から取るのが最も扱いやすい方法です。
ACC電源はキーオンに連動して通電するため、エンジンが動作している時のみドラレコが作動し、キーオフ時には自動的に停止します。
これにより、バッテリーの無駄な消耗を防ぎつつ、日常走行時の映像を確実に記録できます。
一方、駐車監視機能を使用する場合には、常時電源を併用する必要があります。
常時電源はキーオフでも通電を維持するため、駐車中の当て逃げやいたずらなどを記録できる利点があります。
ただし、この場合は電圧監視機能付きの電源ユニットを併用し、バッテリー電圧が一定値(たとえば11.8V)を下回った場合に自動で電源を遮断するように設定することが推奨されます。
こうしたユニットは、電装系の安全性を確保するためにも有効です。
(出典:国土交通省 自動車局「自動車の電気装置に関する基準」)
配線とノイズ対策のポイント
前後カメラを設置する際には、配線の取り回しにも注意が必要です。
特に以下の点を意識することで、誤作動や配線トラブルを防げます。
- 高温部を避ける:
エンジンやマフラー周辺は熱がこもるため、被覆の劣化やショートの原因となります。必ず耐熱チューブを使用し、最低でも10cm以上離して固定します。 - 可動部への干渉防止:
ハンドル可動部やサスペンション周辺では、動きに追従できる余長を確保し、無理なテンションがかからないようにします。 - 高電流線との分離:
ドラレコの映像信号は微弱なため、ヘッドライトやホーンなどの高電流ラインと束ねるとノイズを拾いやすくなります。配線は5cm以上離して別ルートで取り回すと安定します。 - アースの取り方:
アースは必ず車体の金属部分に確実に接続し、塗装面を削って導通を確保します。接触抵抗が高いと電圧が不安定になり、録画が停止するケースもあります。
もし録画中にノイズや映像の乱れが発生する場合は、フェライトコアを電源ケーブルに装着することで高周波ノイズを低減できます。
ドラレコ専用のノイズフィルターも有効で、特にインジェクション制御や電子スロットル車では推奨されます。
電源取り出しハーネスの選び方と取り付け手順

ハーレーで電装品を追加する際に、最も安全かつ確実な方法が「電源取り出しハーネス」を使用することです。
この専用ハーネスを利用すれば、純正配線を切断せずに電源を分岐でき、保証や車体制御システムに影響を与えにくくなります。
適合確認のポイント
電源取り出しハーネスを選ぶ際は、以下の要素を必ず確認してください。
- 適合年式と車種コード
ハーレーは年式ごとにカプラー形状や配線極性が異なります。特に、CAN通信(Controller Area Network)を採用している2011年以降のモデルでは、適合確認が必須です。誤ったハーネスを接続すると通信エラーを引き起こす可能性があります。 - 許容電流と分岐数
使用する電装品の総消費電流を合計し、それを上回る容量を持つハーネスを選びます。たとえば、USB×2ポート(3A)+ドラレコ(1A)の場合、合計4A以上に対応する製品を選定するのが安全です。 - 防水性と耐久性
ハーネスのカプラー部には防水パッキンが備わっているものを選ぶと、雨天走行時も安心です。特にフェンダー下やエンジン付近に配線を通す場合は、IP67相当の防水性能を確認しましょう。
取り付けの基本手順
- 安全対策としてバッテリーマイナス端子を外す
感電防止やショート防止のため、作業前には必ずマイナス端子を外します。 - カプラーを正しく接続
カプラーの爪が確実にロックされるまで差し込み、半挿しの状態で使用しないよう注意します。 - 分岐後の配線処理
各機器には個別のヒューズ(1~5A)を設け、トラブル時の切り分けを容易にします。ヒューズホルダーは防水キャップ付きのものを選び、取り付け位置はアクセスしやすい箇所に設置します。 - 耐熱チューブで配線保護
ハーレーはエンジンからの放熱が大きいため、配線には耐熱チューブ(120℃以上対応)を必ず使用します。 - 動作確認と最終チェック
キーオンでの起動、キーオフでの遮断、エンジン始動時の電圧降下時にも正常動作するかを確認します。配線が擦れやすい箇所は、自己融着テープやコルゲートチューブで追加保護します。
正しい施工を行えば、長期間にわたって安定した電源供給が可能となります。
特に、CAN通信対応モデルでは純正電装品との整合性が重要になるため、メーカーが提供する専用ハーネスを使用するのが最も安全です。
M8ソフテイルのアクセサリー電源の位置と接続方法

M8ソフテイルシリーズでは、アクセサリー電源の取り出しが比較的容易に行える構造になっています。
多くのモデルでは、シート下に設けられた「診断カプラー(4ピンまたは6ピン)」や「アクセサリー用カプラー」が使用できます。
これらのカプラーには、キーオン連動のACC電源線が含まれており、追加電装品を安全に接続することが可能です。
電源位置と確認手順
- シートを取り外す
シート下にはメインハーネスが集中しており、右側もしくは中央付近に診断カプラーがあります。 - カプラー形状を確認
M8系は2018年以降のモデルに多く見られ、4ピン丸型または平型カプラーが採用されています。形状が合わない場合は変換アダプターを利用します。 - テスターで極性を確認
キーオン時に通電するピンをテスターで測定し、12Vが確認できる箇所をACC電源として利用します。
接続と安全管理
接続時は、専用ハーネスを使用して純正配線を損なわないようにします。
圧着端子は専用工具(ラチェットタイプ圧着ペンチ)で確実に固定し、緩みやすいギボシ端子の使用は避けた方が無難です。
ヒューズ容量は、接続する電装品の消費電流に合わせて設定します。
一般的に、USB電源は2A、ドラレコは1A前後が目安です。
振動対策として、配線はフレーム沿いに固定し、可動部や熱を持つ部品との干渉を避けます。
エンジン振動が強いハーレーでは、タイラップを2重固定する、もしくは耐震ゴムクッションを介して配線を保持すると効果的です。
さらに、雨天走行時の信頼性を確保するため、コネクター部にはシリコングリスを塗布し、防水キャップを装着します。
露出部は防水テープで巻き、定期的な点検を行うことで長期的な安定性が維持できます。
M8ソフテイルは構造的にカスタム性が高いモデルですが、電子制御系(ECMやBCM)への影響を最小限にするためにも、メーカーが指定するアクセサリー電源カプラーを優先して使用することが推奨されます。
(出典:ハーレーダビッドソン公式パーツカタログ )
ハーレーのアクセサリー電源の取り方の車種別ガイド
- ダイナのアクセサリーの電源の取り方と配線のポイント
- fxlrsソフテイルの電源の取り出しの実践的な手順
- ミルウォーキーエイトを搭載のスポーツスターの電源取り出し方法
- ローライダーstのacc電源の取り出しと注意点
- ウルトラのACC電源の取り方とカスタム時の留意点
ダイナのアクセサリーの電源の取り方と配線のポイント

ハーレー・ダイナシリーズは、構造的に配線スペースが比較的広く、アクセサリー電源の取り出しや増設がしやすい車種です。
電装カスタムを行う際は、どの電源を利用するか、そしてどのように配線を処理するかが安全性と信頼性を大きく左右します。
主な電源取り出し箇所としては、シート下または左サイドカバー内のヒューズボックス、アクセサリー用カプラーが実用的です。
USB電源やETC、ドライブレコーダーなど、比較的軽負荷な機器(1〜3A程度)であれば、ACC系統(キーオン連動)からの分岐で十分対応できます。
ただし、補助灯やグリップヒーター、電熱ウェアなどの大電流機器(合計で5A以上)を複数接続する場合は、リレーを介してバッテリー直結で給電し、ACCで制御する二段構成を採用するのが最も安定します。
この構成により、既存の回路へ余計な負荷を与えることなく安全に電力を供給できます。
配線経路は外観と整備性を両立させることが重要です。
フレームの内側を通すことで見た目を損ねず、メンテナンス時にも干渉を避けられます。分岐点はアクセスしやすい位置にまとめ、配線色やタグによって識別しやすくしておくと、後の点検や増設作業が格段に効率的になります。
さらに、ダイナシリーズは振動が大きいため、配線の固定と防振対策も欠かせません。
タイラップでの固定時には、金属フレームと直接触れないよう保護チューブを挟むと断線防止に効果的です。
アースポイントは塗装を剥がした金属面に確実に取り、ボルト締結後は導電グリスを塗布すると腐食防止にもなります。
なお、近年のモデルでは一部の制御系統にCAN通信が導入されているため、誤った箇所から電源を取ると通信エラーを引き起こす可能性があります。
施工前には必ずサービスマニュアルで配線図を確認し、純正電源カプラーを利用するのが安全です。
(出典:ハーレーダビッドソン公式サービス情報ポータル )
fxlrsソフテイルの電源の取り出しの実践的な手順

FXLRS(ローライダーS)は、M8ソフテイル系の中でも高性能な電子制御システムを採用しており、正しい手順での電源取り出しが特に重要です。
誤った配線作業を行うと、ABSやECM(エンジンコントロールモジュール)に影響を与える可能性があるため、手順を厳守する必要があります。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外す:
通電状態のままカプラーを抜き差しすると、ECUやセンサーへの過電流が発生するおそれがあります。 - アクセサリーカプラーまたはヒューズボックスを確認:
これらの部位はキーオン連動のACC電源が取りやすい位置であり、USB電源やETCなどの低電流機器には最適です。
専用のハーネスをプラグインすることで、純正配線を傷めることなく安全に分岐できます。 - バッテリー直結+ACC制御の構成を採用:
補助灯や加熱グリップなどの高出力機器(5〜10A以上)は、リレーを併用してバッテリー直結+ACC制御の構成を採用しましょう。
この場合、ヒューズ容量は機器の定格電流の1.25倍を目安に選定します。たとえば定格4Aの補助灯なら5Aヒューズを設定し、過剰遮断や保護不足を防ぎます。
配線ルートと固定方法
FXLRSでは、タンク下からヘッドライトハウジング内へ配線を通すパターンが一般的です。
可動部(ハンドル・ステアリングコラム)との干渉を避けるため、余長を5〜10cm程度確保し、動きに追従できるよう配線スリーブで保護します。
タイラップ固定時は、電線を強く締めすぎると被覆が損傷するため、軽く動く程度のテンションで留めるのがコツです。
配線が完了したら、キーオン時・キーオフ時・始動時の各状態で動作確認を行い、電圧降下が生じていないかテスターでチェックします。
エンジン始動時には一時的に電圧が11V台まで低下するため、電源ユニットが誤作動しないか確認することも大切です。
ミルウォーキーエイトを搭載のスポーツスターの電源取り出し方法

ミルウォーキーエイト(Milwaukee-Eight)エンジンを搭載したスポーツスター系モデルは、従来のXLシリーズよりも電子制御が高度化しており、電源取り出しには正確な知識と丁寧な施工が求められます。
主な電源取り出しポイントは、シート下や左サイドカバー内のアクセサリーカプラーです。
ここからキーオン連動のACC電源を取得でき、USB電源、ETC、ドラレコなどの周辺機器を安全に接続できます。
専用の電源取り出しハーネスを使用することで、配線加工なしで取り付け可能です。
配線設計とスペース管理
スポーツスターはコンパクトなフレーム設計のため、配線スペースが限られています。
配線を効率的に収めるには、ハーネスの長さとルートを事前に設計することが不可欠です。
配線を余らせすぎると巻き込みや擦れの原因となるため、最短距離で安全な経路を選びます。
特にリアフェンダー周辺は振動と湿気が多いため、コルゲートチューブや熱収縮チューブで保護し、タイラップでフレームに確実に固定します。
電装品ごとに独立したヒューズを設けることで、トラブル時の切り分けが容易になります。
防水対策と信頼性確保
ハーレーは雨天走行や高湿環境でも使用されるため、コネクター部分の防水処理は非常に重要です。
上向きのコネクター口には防水キャップを装着し、端子内部にシリコングリスを塗布して酸化防止を行います。
こうした処理により、接触不良や電圧降下を防ぎ、長期的な信頼性を確保できます。
また、スポーツスターの一部モデルでは電子制御スロットル(ETCスロットル)やEFIシステムとのノイズ干渉が報告されているため、電装系統を追加する際はノイズフィルターやフェライトコアの装着も検討すると安心です。
最後に、施工後はエラーコード表示の有無を確認し、ECU診断カプラーを通じてシステムチェックを行うと安全です。
ローライダーstのacc電源の取り出しと注意点

ローライダーSTはフェアリングを装備した構造上、前方までの配線ルートが他のモデルよりも複雑です。
そのため、ACC電源を利用する際には「配線固定」と「防振対策」を徹底することが信頼性確保の第一歩となります。
電源の取り出し位置と配線構成
ACC電源は、キーオンで通電し、キーオフで遮断されるため、USB電源やナビ、ドライブレコーダーなどの常用アクセサリーの電源源として最適です。
ローライダーSTでは、シート下のアクセサリーカプラーまたはヒューズボックス内のACC系統から分岐させる方法が一般的です。
これにより、走行中の安定した電力供給が可能になります。
高負荷を伴う補助灯やグリップヒーターなどを同時に使用する場合は、リレーを用いたバッテリー直結方式を採用し、ACC電源をリレー制御信号として利用します。
これにより、ACC系統への過負荷を防ぎつつ、電装品の安定動作を維持できます。
リレーは防水型の40Aタイプを選び、ハーレー純正ハーネスと整合性のあるギボシ形状を使用するとメンテナンス性も向上します。
フェアリング構造を考慮した配線処理
ローライダーSTのフェアリング内部は熱がこもりやすく、また振動が伝わりやすい構造です。
そのため、配線を束ねすぎないことが重要です。
適切な線径(USBなどは0.75sq、補助灯は1.25sq以上)を選び、余裕をもたせたルーティングを行うことで断線リスクを軽減できます。
さらに、配線固定には耐振タイラップやクッションテープ付きのホルダーを使用すると、走行中の共振を防止できます。
アース処理とメンテナンス性
アースポイントは、塗装を剥離した金属面を確保したうえで確実に接続し、ボルト締結後は防錆グリスを塗布して腐食を防止します。
特にローライダーSTのようなアルミ部材を多く使用する車体では、電蝕を防ぐ意味でもこの処理が不可欠です。
結線部は点検時のアクセスを考慮し、点検口から手が届く位置にまとめておくと便利です。
フェアリングを脱着せずに導通確認やヒューズ交換ができる構成にしておくと、トラブル時の復旧が容易になります。
なお、電装品を増設する際は、純正電装系との干渉防止を最優先に考え、CAN通信システムに直接接続しないよう注意が必要です。
特に現行モデルでは電子制御回路が高密度化しており、誤った電源取り出しはエラーコードを誘発する可能性があります。
ウルトラのACC電源の取り方とカスタム時の留意点

ハーレーダビッドソンのウルトラシリーズは、ツーリングモデルとして多くの電装品を搭載できる構造が特徴です。
そのため、ACC電源の取り方や配線設計を正しく行うことで、利便性と安全性の両立が実現します。
電源の取り出し位置と分配構成
ウルトラでは、フェアリング内部やツアーパック周辺に複数のアクセサリーポイント(Accessory Port)が標準装備されています。
キーオン連動のACC電源を利用すれば、ナビゲーション、USBチャージャー、ドライブレコーダーなどを自動的に起動でき、利便性が格段に向上します。
複数の電装品を同時に使用する場合は、マルチ電源ユニット(電源分配ボックス)を導入するのが安全です。
このユニットにより、各機器に独立したヒューズを設けられ、異常時に特定の回路だけを遮断できます。
ヒューズ容量は以下のような目安で設定するとよいでしょう。
| 電装品 | 消費電流の目安 | 推奨ヒューズ容量 |
|---|---|---|
| USB電源 | 約2A | 3A |
| ナビ | 約3A | 5A |
| ドライブレコーダー | 約1A | 2A |
| グリップヒーター | 約5A | 7.5A |
| 補助灯(LED) | 約4A | 5A〜7.5A |
また、ウルトラは大型フェアリング内部に多くのハーネスが集中しているため、サービスマニュアルの配線図を確認しながら、既存ラインと干渉しないルートで固定することが大切です。
発電能力と消費電力のバランス
長距離走行では、ナビ、充電機器、ドラレコ、インカムなどの連続稼働により電力消費が増加します。
ハーレー・ウルトラのオルタネーター出力は一般的に50A(約600W)前後ですが、アイドリング時はその半分程度まで低下します。
そのため、全消費電力が発電量を超えないよう管理することが重要です。
電力バランスを把握するためには、各電装品の消費電力を合計し、常時稼働時の余裕を20〜30%残すよう設計します。
たとえば、総消費が400Wの場合、発電量600Wのうち200Wを余裕として確保するのが理想的です。
防水処理と長期信頼性
ウルトラは雨天や洗車時に水がフェアリング内部へ侵入することがあります。
配線接続部は防水コネクターを使用し、露出部には自己融着テープやシリコーンシーラントで防水処理を施します。
ツアーパック内に電源ユニットを設置する場合は、通気口を確保して熱を逃がしつつ、ゴムグロメットで水滴の侵入を防ぐと効果的です。
カスタム時には、純正配線の改変を避け、必ず「アクセサリーカプラー」や「分岐ハーネス」を使用して施工することで、保証や電子制御系への影響を回避できます。
このように、ウルトラのACC電源を正しく取り扱うことで、長距離ツーリング時の電装品運用が安定し、快適な走行環境を維持できます。
まとめ|ハーレーのアクセサリー電源の取り方を正しく理解しよう
- 常時電源・ACC電源・イグニッション電源の違いと役割を正しく理解して安全に使い分ける
- USB電源やドライブレコーダーはACC連動としバッテリーの待機電流を効率的に管理する
- ヒューズボックスからの電源取り出しは便利だが容量超過を避け適正な回路設計を行う
- 大電流機器はリレーを併用しバッテリー直結供給とACC制御を分離して安全性を高める
- 電源取り出しハーネスは適合年式やCAN通信対応を確認し許容電流に余裕を持たせて選ぶ
- 圧着端子の加工精度と防水処理を徹底し振動や腐食に強い信頼性の高い配線を構築する
- 配線は最短経路を意識して取り回し線径を適正化し電圧降下と発熱を最小限に抑える
- アースは塗装を剥離した確実な金属面を選び導通確認と防錆処理を同時に実施する
- M8ソフテイルでは診断カプラーやACCカプラーを利用して安全かつスマートに接続する
- ダイナはサイドカバー内とシート下を有効活用し保守性と拡張性を両立させた配線設計
- FXLRSはヘッドライト内に配線を通す際に余長確保と固定方法を工夫して断線を防ぐ
- スポーツスターは狭いスペースに配線を整理し最短距離で安全な電源経路を確保する
- ローライダーSTはフェアリング内部の熱と振動を考慮し耐熱材と防振固定を組み合わせる
- ウルトラはマルチ電源ユニットで各機器を独立保護し長距離走行でも安定稼働を維持する
- 施工完了後はキーオンオフと始動時の動作を確認し電圧変動や誤作動の有無を点検する