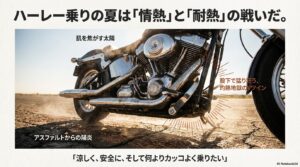ハーレーのマフラーの車検対応について調べている方の多くは、なぜマフラーが車検に通らないのか、その具体的な理由や、実際にハーレー車検をどうしているのかといった実情を知りたいと考えています。
本記事では、基準を満たすための鍵となるJMCAの考え方をはじめ、エンジン世代ごとの特徴であるツインカムとM8の違いを整理します。
さらに、スクリーミンイーグルやバンス&ハインズのマフラーの実用性、ソフテイルやダイナの適合ポイント、ローライダーSTのマフラーの車検対応の注意点までを、失敗や後悔を避けるための実務的な視点で詳しく解説します。
- 年式と規制に基づく車検の合否ポイント
- JMCAやEマーク等の認証の読み解き方
- エンジン世代別と車種別の適合と注意点
- 実務で役立つ準備手順と事前チェック
ハーレーのマフラーの車検対応の基礎
- マフラーの車検通らない原因とは
- ハーレー車検はどうしてる?対策とは
- マフラーのJMCAの基準について
- 車検対応マフラーのツインカムの要点
- 車検対応マフラーのM8の注意点
マフラーの車検通らない原因とは

車検で不合格になりやすいポイントは、大きく分けて騒音と排ガスの二つです。
騒音側では、近接排気騒音の上限を超えるケースが最も多く見られます。近接排気騒音は、停車状態で規定回転数(最高出力回転数の50~75%相当)までエンジンを上げ、排気口から斜め45度・距離50cmの位置で騒音計測を行います。
年式により基準の見方が異なり、2001年以降は絶対値の上限が厳格化、さらに新制度では新車時に確認された値に対して使用過程で+5dB以内であることを求める相対値規制が導入されています(出典:国土交通省 自動車騒音規制の推移)。
構造によっても音量は変わります。
ドラッグパイプのようにサイレンサー容量が極端に小さい、あるいは消音機構が簡素なレイアウトは、排気抵抗が減るぶん音圧が上がりやすく、基準超過に直結しがちです。
長尺で内部容積の大きいサイレンサー、あるいは多室構造・高密度グラスウールを用いたタイプほど、同出力での騒音抑制がしやすい傾向があります。
排ガス側では触媒(キャタライザー)の有無が要となります。
純正で触媒を内蔵する車両に対し、触媒なしのフルエキへ交換すると、CO・HCの値が上がりやすく、結果として不適合となる可能性が高まります。
さらに、消音材の経年劣化、触媒の活性低下、排気漏れ(フランジやガスケットの当たり不良)、O2センサーの異常、燃調ずれ(チューニング後の補正不足)なども数値悪化の原因です。
騒音と排ガスの両輪で整合を取り、年式に沿った認証・構造・計測条件を満たしているかを一つずつ確認する姿勢が、合格への近道になります。
年式と騒音の考え方(要点整理)
| 規制の区分 | 近接排気騒音の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 1986年~2001年9月 | 99dB以下の絶対値が目安 | 歴史的な上限の参照値として扱われます |
| 2001年10月~2013年 | 94dB以下の絶対値が目安 | 脱着容易な簡易バッフルは不適とされがち |
| 2014年4月以降 | 型式認証値に対し+5dB以内 | 加速走行騒音規制と連動、相対値で確認 |
上表の数値は、各時期の代表的な見方を整理したものです。
実際の判定は、車両の型式・備考欄・ラベル表記や、現行の相対値規制の適用可否に基づいて行われます。
車検証と車体のラベル、装着マフラーの認証表示を合わせて確認することが大切です。

ハーレー車検はどうしてる?対策とは

結果を左右するのは、日常整備と直前準備の質です。
まず、車両の年式、型式ごとの認証値、純正触媒の有無、O2センサーの数と配置、電子制御バルブの有無を、パーツリストと現車で突き合わせます。
次に、マフラーのJMCAプレートやEマーク、型式刻印の視認性を確認し、錆や傷で判読不能になっていないかを点検します。
ここが曖昧だと検査官とのコミュニケーションに齟齬が生じやすく、再検につながりかねません。
チューニング済み車両では、暖機の手順が数値に直結します。
触媒は所定温度に達して初めて浄化性能を発揮するため、ウォームアップリッチが収束し、アイドリングが安定してから計測に臨む流れを意識します。
学習値(トリム)のリセット直後は一時的に濃い・薄いが出やすいため、直前に大幅な書き換えを行った場合は、数十kmの慣らしや再学習のプロセスを挟むと安定しやすくなります。
不安が残るときは、予備検査場での事前計測が有効です。
数千円程度で近接騒音と排ガスの簡易チェックを済ませ、傾向を掴んだうえで本番へ向かいます。
あわせて、以下の基本点検を整えておくと、無駄な再検の回避につながります。
- 消音材の劣化・焼損の有無と、サイレンサー内部の固定状態
- 排気漏れの点検(フランジ、差し込み、ジョイント部のスス痕)
- アイドリング回転数と同調の見直し、エアクリ周りの二次エア対策
- チューニング内容の再確認(O2フィードバック範囲、触媒保護設定)
これらを押さえることで、当日の計測値がブレにくくなり、スムーズに合格ラインへ収めやすくなります。
マフラーのJMCAの基準について

JMCA認証は、国内の騒音・排ガス要件を満たしたアフターマフラーであることを示す目印として広く用いられます。
量産前の試験段階で、加速走行騒音や近接排気騒音、必要に応じて排出ガス試験を通過した製品にプレートや刻印が付与されます。
現場の車検では、JMCAやEマークの表示、刻印の可読性、消音機構の固定状態などが確認項目となり、改変がなければ適合判断に進みやすくなります。
一方で、使用過程の劣化は無視できません。
消音材(グラスウール)の飛散・圧縮、パンチングパイプの焼損、触媒の被毒・融解、継手部の排気漏れは、音量上昇やCO・HC悪化の典型的な要因です。
加えて、刻印部の腐食や外装の傷で表示が読めない場合は、適合品でも確認が取れずに不利になる恐れがあります。
点検時は、外観・表示・内部状態・取り付けの四点をセットでチェックし、必要に応じて消音材のリパック、ガスケット交換、触媒入り構成への復帰、固定ボルトの増し締めを実施するとよいでしょう。
製品が認証済みであることに加え、現物が当初の性能を保っていることを示せれば、審査はぐっとスムーズになります。
車検対応マフラーのツインカムの要点

ツインカム世代(1999~2017年頃)のハーレーは、アフターマーケットマフラーの選択肢が最も豊富な年代といわれています。
2-into-1タイプ、独立管(デュアル)、ショートドラッグスタイルなど、多様なレイアウトが存在し、音質・トルク特性・見た目を重視したカスタムがしやすい反面、年式ごとの排ガス規制とO2センサー構成に注意が必要です。
特に2007年以降のインジェクションモデルでは、燃調マップの最適化が必須となります。
燃料噴射量の補正が不十分な状態で社外マフラーを装着すると、チェックランプが点灯したり、空燃比が極端に薄くなって触媒が過熱する恐れがあります。
また、O2センサーの仕様にも世代差があります。
前期は狭帯域センサー(ナローバンド)が多く、後期は広帯域(ワイドバンド)タイプが採用されるケースがあります。
センサーのボス径や配置位置を誤ると、適切な燃焼制御が行えず、燃費悪化やエンジンノッキングを引き起こすリスクがあります。
このため、社外フルエキ装着時には「センサーボス径」「配置」「カプラー形状」の3点確認を行うことが不可欠です。
排ガス対策として、スリップオンマフラーで純正エキパイや触媒を残す構成は、排出ガス値の上昇を抑えやすい現実的な選択肢です。
音量も純正触媒が音圧をある程度吸収するため、近接排気騒音の管理が容易になります。
一方、フルエキゾースト(エキパイから交換するタイプ)に変更する場合は、「触媒入り構造」または「JMCA/Eマーク認証済み」の確認が必須です。
刻印の有無を記録し、整備記録簿やメーカーの仕様書を提示できるようにしておくと、検査時の信頼性が高まります。
さらに、ツインカムモデルはマフラー交換によるトルク特性の変化が顕著で、特に低回転域のドンつき(急激なトルク変化)やバックファイアを抑えるために、ECM(エンジンコントロールモジュール)の再マッピングやサブコンの導入が検討されます。
これらの燃調補正を適切に行うことで、燃焼温度やCO・HC値の安定化にもつながります。
このように、ツインカム世代では「音」「ガス」「燃調」の三点をバランスよく管理することが、車検をスムーズに通す鍵といえます。
(出典:国土交通省 自動車排出ガス規制概要)
車検対応マフラーのM8の注意点

M8(ミルウォーキーエイト)世代(2017年~)のハーレーは、排気ガスおよび騒音規制がさらに厳格化されています。
触媒容量が拡大され、O2センサーの検知精度も高まったため、制御系がより複雑になっています。
可変バルブ(アクティブバルブ)を備えた電子制御マフラーでは、エンジン回転やスロットル開度に応じて排気経路を切り替え、静音モードとハイパフォーマンスモードを自動制御します。
この静音モードこそが、騒音規制に適合するための設計ポイントです。
ただし、カムシャフトの変更やECUチューニングによって燃焼タイミングがずれると、可変バルブの開閉タイミングと制御マップが噛み合わず、基準値を超える可能性があります。
これはウォームアップの不十分や触媒温度の低下時にも顕著に現れるため、車検直前の暖機手順が非常に重要になります。
M8エンジンのO2センサーは高応答タイプが採用されており、触媒の状態変化をリアルタイムで監視しています。
触媒温度が約300~400℃に達していないと反応が安定せず、CO/HC値が不安定になりやすい傾向があります。
したがって、車検前は最低でも10分程度のアイドリング暖機を行い、センサー学習値(ショート・ロングトリム)が平常範囲に戻った状態で測定を受けることが望ましいとされています。
さらに、電子制御バルブの誤作動を防ぐためには、検査前に以下の項目を確認しておくことが推奨されます。
- ECUのエラーコードを診断機でクリアしておく
- バルブアクチュエーターの動作音や可動範囲を点検する
- サーボモーターのワイヤー張りすぎ・たるみを修正する
- 排気漏れ(ガスケットやフランジのシール不良)を解消する
特に、音量可変タイプのマフラーでは「静音モード以外」で計測されると不利になるため、検査時のモード選択にも注意が必要です。
最近の検査場では、ECU通信でエンジン回転をモニタリングするケースも増えており、アイドリング回転数やアクセル操作の僅かな差が結果に影響します。
M8世代では、エンジン制御とマフラー構造が密接にリンクしているため、整備・燃調・操作のすべてを一体で管理することが車検対応の最大のポイントといえます。
ハーレーのマフラーの車検対応の選び方
- スクリーミンイーグルマフラーは車検対応か
- バンス&ハインズの車検対応マフラーを解説
- ソフテイルの車検対応マフラーの選択
- 車検対応マフラーのダイナの適合
- ローライダーSTのマフラーについて解説
スクリーミンイーグルマフラーは車検対応か

スクリーミンイーグルはハーレー純正パフォーマンスブランドとして知られ、純正開発ならではの高い信頼性と適合性を誇ります。
ハーレーダビッドソンジャパンが正式に扱うマフラーラインナップは、国内の車検基準や排出ガス規制を前提に設計されており、車両の制御システムや触媒位置と完全に整合しています。
したがって、フィッティング精度が高く、装着後のエラーコード発生やO2センサーの誤作動が起こりにくい点が大きな魅力です。
代表的なシリーズであるストリートキャノンは、純正比で力強い低音を響かせつつも、近接排気騒音を規制値内に抑え、排ガスのクリーン性能を確保しています。
さらに、排圧設計が緻密で、エンジンの出力特性を損なわずにトルクの厚みを感じられる仕様になっています。
消音性能とパフォーマンスの両立を目指した設計思想が特徴です。
選定時には、以下のポイントを確認しておくと安心です。
- 品番ごとの適合年式と排ガス規制区分
- 触媒の有無と配置位置(モデルによって異なる)
- エンド形状・口径の違いによる排気効率と音量変化
- バッフル構造や交換可否
アイドリング時だけでなく実走行時のこもり音や共振の少なさも、日常使用の快適性を左右します。
また、価格は社外製に比べて高めですが、ディーラーでの整備対応や保証継続性、将来的な下取り評価などの面で長期的なメリットがあります。
これらを総合的に考えると、コストパフォーマンスの高さは決して低くありません。
(出典:ハーレーダビッドソン公式サイト「スクリーミンイーグル パーツ情報」)
バンス&ハインズの車検対応マフラーを解説

バンス&ハインズ(Vance & Hines)は、アメリカを代表するエキゾーストブランドで、独自のデザイン性と重厚なサウンドで世界的な人気を誇ります。
しかしながら、同ブランドの製品の中には、レース専用や北米仕様として設計されたモデルも多く、国内の車検制度を前提にしていないものが存在します。
そのため、見た目が同じでも、型番や販売地域によって車検適合性が異なる点には特に注意が必要です。
近年では、PCX触媒を搭載したシリーズや、Eマークを取得したヨーロッパ仕様が登場し、日本国内でも合法的に使用できるモデルが増えつつあります。
これらは純正比で約3〜5dB高い音圧を持ちながらも、規定内に収まるよう設計されています。
実際の車検では、触媒の有無、年式適合、近接騒音値が判断基準となります。
選定時には、以下の手順で確認を進めると失敗がありません。
- スリップオンで純正触媒を残す構成か、触媒付きフルエキかを決定
- 品番・認証ラベル(Eマーク、JMCA刻印)の有無を確認
- 実走行時の音質とこもり音のバランスを試聴で確認
- 熱対策(シート下の遮熱、タンデムステップ周りのクリアランス)を考慮
また、音量が上がりやすい製品では、定期的なグラスウール交換や追加バッフルの導入が有効です。
特にツーリングモデルなどでは、長時間走行時の疲労軽減にもつながります。性能だけでなく、安全性と快適性の観点からも、実測データをもとに選ぶことが大切です。
ソフテイルの車検対応マフラーの選択

ソフテイルシリーズはハーレーの中でもカスタムの自由度が高く、クラシックからモダンまで幅広いスタイルを楽しめるモデルです。
そのため、マフラー選びでは「デザイン」「性能」「車検適合性」のバランスが重要になります。
特にM8エンジン以降のモデルでは、触媒容量やO2センサー配置が複雑化しているため、適合確認を怠ると排ガス数値が基準を超えるリスクがあります。
マフラー形状には独立管(デュアル)、2-into-1、ショートタイプなどがありますが、それぞれに特徴があります。
- 独立管タイプ:
クラシカルな見た目で人気が高いが、音量が大きくなりやすい。 - 2-into-1タイプ:
排気効率が高く、トルク特性を改善しやすい。 - ショートタイプ:
軽量でスポーティだが、近接騒音値が上がりやすく、車検時のリスクが高い。
短いマフラーほど音圧が上昇し、逆に容量のある長尺サイレンサーほど静粛性を確保しやすい傾向があります。
そのため、車検対応を重視するなら、スリップオン+純正触媒の構成が最も安定した選択肢となります。
この構成であれば、排ガス浄化機能を維持しながらも、サウンドチューニングの幅を持たせることが可能です。
さらに、外観デザインだけでなく、実際の走行時に足や荷物との干渉がないか、タンデム走行時に熱がこもらないかといった実用面の確認も欠かせません。
特にソフテイルのようなカスタムベースモデルでは、見た目と実用性を両立するマフラー選びが車検合格への近道になります。
車検対応マフラーのダイナの適合

ダイナシリーズは、ハーレーらしいラバーマウント構造とツインショックサスペンションによる独特のフィーリングが特徴です。
そのため、車検対応マフラーを選ぶ際は、性能・スタイル・整備性のバランスを重視することが重要です。
特に、走りの質を高めたいユーザーには、排気干渉を抑えてトルクを向上させる2-into-1レイアウトが人気を集めています。
この構成は、排気流速の安定化とエンジンレスポンスの向上に寄与し、車検時にも音量・排気効率の両立が図りやすいのが利点です。
車検対応を前提とする場合、アップタイプの2-into-1マフラーを選ぶと、コーナリング時のバンク角を確保しやすく、かつ大容量サイレンサーによって騒音を効果的に抑えられます。
近接排気騒音の基準は車両年式により異なりますが、一般的には2001年以降の車両で94dB以下(または型式認証値+5dB)が目安とされています。
これを超える製品は、バッフル交換や消音材リフレッシュが必要になる場合があります(出典:国土交通省「自動車騒音規制の概要」)
また、O2センサー仕様にも年式差があり、2007年以降のインジェクションモデルではセンサー径(主に18mmまたは12mm)や配置位置が異なります。
これらの違いを無視してマフラーを装着すると、空燃比の異常検出によるチェックランプ点灯や燃調の乱れを招く恐れがあります。
購入時には、必ず「対応するボス径」「センサー配置」「カプラー形状」を確認し、適合表をもとに照合することが必要です。
さらに、ダイナは2017年で生産を終了したため、現行マフラー製品の中には「ダイナ系統(FXD系)」への適合記載が曖昧なものも見受けられます。
そのため、以下の点を事前に確認するとトラブルを防止できます。
- メーカー公表の品番と適合表の照合
- 実車側の配線取り回し・カプラー形状・センサーハーネスの長さ
- ステー穴位置やブラケット角度の一致確認
- フレームやステップとの干渉の有無
これらを入念にチェックしておくことで、取り付け時のトラブルや車検時の指摘を回避でき、快適な走行と合法性を両立できます。
特に長期使用車両では、マフラーステーの金属疲労やガスケットの劣化も確認し、取り付け精度を確保しておくことが重要です。
ローライダーSTのマフラーについて解説

ローライダーSTは、M8(ミルウォーキーエイト)エンジンを搭載したスポーツツアラーとして登場し、その走行性能とデザイン性から高い人気を誇るモデルです。
純正装備のハーフカウルやサイドバッグを前提とした構造のため、マフラー選定時には外観上のフィッティングだけでなく、クリアランス確保と熱対策が極めて重要になります。
特にバッグやスタンドとの干渉、マフラーエンドの取り回し角度によっては、走行中の振動で樹脂パーツを損傷するリスクもあるため注意が必要です。
ローライダーSTはM8世代であるため、触媒とO2センサーの制御が高精度化しています。
さらに、電子制御バルブ(アクティブバルブ)を備えるマフラーでは、ECUの信号により排気経路が自動的に切り替わる構造になっており、「静音モード」と「開放モード」の両方が存在します。
静音モード時の近接騒音値は車検基準に適合するよう設計されていますが、開放モードでは5〜10dB程度音量が上昇することもあります。
そのため、検査時にどのモードで測定されるかを理解し、静音モードを確実に有効化しておくことが不可欠です。
また、電子制御マフラーの制御ロジックを理解することもポイントです。
アイドリング時や一定負荷時にバルブを閉じ、加速時に開く設定が多く採用されており、検査中のエンジン回転変化に応じてバルブが自動作動することもあります。
可変機構付きマフラーを選ぶ際は、制御ユニットが純正ECUと通信できる仕様であること、またEマークまたはJMCA認証を取得していることを確認しましょう。
車検対応を前提とした選定では、以下の実機チェックが重要です。
- バッグやステーとの干渉確認(特に右側パニア)
- スタンド格納時のクリアランス確保
- マフラーエンドと地面との接地角度
- 排気熱がシート裏やサイドバッグへ伝わらない構造かの確認
また、街乗りからワインディングまで幅広く使用するユーザーにとって、熱対策と音質のバランスは快適性を左右する重要要素です。
長距離ツーリング時に排気熱がライダーの脚部や荷物へ影響しないよう、ヒートシールドや断熱バンテージを併用するのも有効です。
ローライダーSTはそのスタイル上、見た目と実用性を高次元で両立させるマフラー選びが求められます。
ハーレーのマフラーの車検対応について要点まとめ
- 車検は騒音と排ガスの二軸で判定され、年式ごとに異なる基準値を理解して対策することが重要です。
- スリップオンで純正触媒を残す構成は排ガス値が安定しやすく、車検適合を得やすい現実的な選択です。
- JMCAやEマークの刻印は車検適合の信頼を左右するため、確認と記録を確実に行うことが欠かせません。
- 消音材や触媒が劣化すると新品時の性能が発揮できず、騒音や排ガス数値の悪化につながる恐れがあります。
- ツインカムは年式ごとに異なるO2センサー仕様へ適合させ、燃調と制御を整えることが車検合格の鍵です。
- M8は触媒容量と制御が精密化しているため、暖機手順の違いが数値結果に影響する点を理解して準備します。
- ドラッグパイプなどサイレンサーの少ない構造は音量が上がりやすく、騒音基準超過のリスクが高くなります。
- スクリーミンイーグルは純正開発による高い適合性と整備性が魅力で、長期的な安定性が評価されています。
- バンスアンドハインズは触媒構造と実測音量を事前に確認し、認証モデルを選ぶことでリスクを抑えられます。
- ソフテイルは全体シルエットとバンク角の両立を意識し、外観と実用性のバランスを取った選定が重要です。
- ダイナは2インツー1構成で排気効率を高めつつ、音量管理と車検対応を両立させることがポイントです。
- ローライダーSTは装備類との干渉や排気熱の影響を事前に確認し、熱管理を徹底することで快適性を維持します。
- 予備検査場での事前計測は音量や排ガス傾向を把握でき、不合格リスクを大幅に減らす効果が期待できます。
- 刻印の判読性や取り付け状態の健全性を維持し、検査官が確認しやすい環境を整えておくことが大切です。
- 燃調やECU学習値を最適化することでCO値やアイドリングが安定し、排ガス試験をクリアしやすくなります。