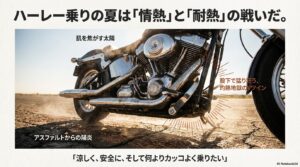ハーレーに乗っていると、ふと目に入る警告灯の点灯に戸惑うことはありませんか?
とくに「ハーレーの警告灯一覧」と検索してこの記事にたどり着いた方は、現在何らかの警告表示に不安を感じているかもしれません。
ハーレーのメーターには、赤やオレンジ、緑などさまざまな色の警告灯が存在し、それぞれが異なる意味を持っています。
中にはエンジンチェックランプが点いたり消えたりして、何が起きているのか判断しにくいケースもあるでしょう。
また、鍵マークの警告灯が突然点灯したり、オーバーヒート警告灯が出てしまったりと、初めての症状に戸惑う場面も少なくありません。
この記事では、バイクのエンジン警告灯には何種類あるのかといった基本から、各警告灯の意味、エラーコードの見方や代表的なエラーコード「p1608」の内容、さらには「警告灯がついたまま走行してもいい?」という疑問にも丁寧に答えます。
加えて、警告灯の消し方やトラブルコードの消し方といった実践的なリセット方法についても詳しく解説していきます。
初めての方でもわかりやすく、かつ正確な情報をまとめていますので、ぜひ参考にして安全なハーレーライフに役立ててください。
- ハーレーの警告灯の種類とそれぞれの意味
- 色別(赤・オレンジ・緑)の警告灯が示す状態
- エンジンチェックランプやエラーコードの確認と対処法
- 警告灯の消し方やトラブルコードのリセット手順
※本記事は「ハーレーダビットソン公式」をはじめ、「ハーレーダビットソン東久留米」など信頼のおけるサイトの情報を中心に調べて執筆しています。
ハーレーの警告灯一覧と意味を徹底解説
- 赤の警告灯が示す危険とは
- オレンジの警告灯が点灯時の注意点
- 緑の警告灯が示す状態とは
- 鍵マークの警告灯の意味と原因とは
- バイクのエンジン警告灯は何種類?
赤の警告灯が示す危険とは

赤い警告灯が点灯している場合は、ハーレーに重大な異常が発生している可能性が高いです。
無理に走行を続けるのではなく、すぐに安全な場所に停車し、状態を確認する必要があります。
なぜなら、赤の警告灯はエンジンやオイル、電装系など、バイクの基本機能に関わる重要なトラブルを知らせるサインだからです。
放置してしまうと、エンジンの焼き付きやブレーキの作動不良といった深刻な事故につながる危険性もあります。
例えば、オイルプレッシャー警告灯が赤く点灯した場合、エンジン内部でオイルが正しく循環していないことを意味します。
オイルはエンジンの冷却や潤滑に欠かせないため、この状態で走り続けると金属部品が摩擦で破損し、エンジン本体の損傷に発展しかねません。
また、冷却系統の異常やバッテリーの電力供給エラーでも赤いランプが点灯するケースがあります。
ただし、イグニッションをONにした直後に一瞬だけ赤の警告灯が点くのは、自己診断機能が作動しているだけの正常な現象です。
この場合は数秒後に自動で消灯します。
このように、赤色の警告灯は「今すぐ対応すべき異常」のサインです。
点灯した際は焦らず、冷静に確認と対応を行うことで、大きなトラブルの回避につながります。
オレンジの警告灯が点灯時の注意点

オレンジの警告灯が点灯した場合は、今すぐ停車する必要はありませんが、何らかの異常がバイクに発生している可能性があります。
走行できる状態ではあっても、放置せずに早めの点検を受けることが重要です。
この警告灯は、主に電子制御系の不具合やセンサー異常を知らせるものです。
エンジンチェックランプやABS(アンチロックブレーキシステム)のランプなどが、オレンジ色で表示されることが多く見られます。
点灯している間は、システムの一部が正常に機能していない状態と考えましょう。
例えば、チェックエンジンランプが点灯しているときは、燃料噴射や点火タイミングの異常、O2センサーの故障などが疑われます。
走行中に急にエンジンの調子が悪くなったり、燃費が大きく低下することもあるため、無視するのは避けたいところです。
一方で、ABSランプが点灯している場合は、通常のブレーキは使えるものの、ABS機能がオフになっている状態です。
これにより、急ブレーキ時にタイヤがロックしやすくなり、特に雨天や滑りやすい路面では大きなリスクになります。
ただし、エンジン始動直後にオレンジのランプが一時的に点灯し、その後消えるケースもあります。
これは自己診断による一時的な点灯で、問題ないことがほとんどです。
逆に、消えずに走行中も点灯し続ける場合は、異常の兆候と判断するべきです。
このような場合、自己判断は避け、速やかにディーラーや整備工場で点検を受けるのが安全です。
小さな異常が重大な故障につながることもあるため、早めの対応が結果的に費用やリスクの軽減につながります。
緑の警告灯が示す状態とは

緑の警告灯が点灯しているときは、基本的に車両に異常があるわけではありません。
これは「正常な作動状態」を示すインジケーターであり、ライダーが安心して操作できるよう補助する役割を担っています。
多くのハーレーでは、緑色のランプはギアがニュートラルであることや、ウインカーが作動していることを知らせるために使われます。
例えば、エンジン始動時にギアがニュートラルに入っていると点灯するニュートラルインジケーターは、エンジン始動の安全確認に欠かせません。
また、左右のターンシグナルを作動させた際にも、それぞれの方向に対応した緑のインジケーターが点滅します。
これは、ウインカーが正しく作動していることを視覚的に確認するためのサインです。
両方が同時に点灯する場合は、ハザードランプが作動していることを示します。
ただし、緑の警告灯であっても異常が疑われるケースがあります。
たとえば、ランプが点灯しない、または常時点灯しているような場合は、配線不良やスイッチの故障、センサーの異常などが原因となっている可能性があります。
このように、緑の警告灯は通常は安心のサインですが、点灯状態に不自然さが見られるときは、念のため点検を受けることをおすすめします。
正しい動作を確認しながら走行することで、安全性と快適さを保つことができます。
鍵マークの警告灯の意味と原因とは

鍵マークの警告灯が点灯している場合、それはハーレーのセキュリティシステムに関連する異常や操作ミスを知らせています。
このマークは、「イモビライザー」や「セキュリティ解除の失敗」に関するサインであることが一般的です。
この警告灯が点灯する主な原因は、キーフォブ(電子キー)との通信不良です。
キーフォブがバイクの近くにない場合や、バッテリー切れによって信号を正しく送れないと、車両側が「鍵が見つからない」と判断し、警告灯を点灯させます。
例えば、ツーリング先で鍵マークが点灯しエンジンがかからない状況になったとき、実はキーフォブのバッテリーが切れていたというケースがあります。
スペアキーやPINコードによる解除が可能なモデルもありますが、事前に方法を確認しておかないと対応に手間取ることになります。
また、イモビライザーやセキュリティモジュールそのものに異常がある場合にも、鍵マークが表示されることがあります。
このようなときは、単純な操作ミスとは異なり、整備士による診断が必要です。
この警告灯が一時的に点いてすぐに消えるのであれば、通信の遅れなど一過性の現象と考えて問題ありません。
しかし、エンジン始動ができない・毎回点灯するなどの症状がある場合は、早めに点検を受けたほうが安心です。
ハーレーの鍵マークの警告灯は、盗難防止や安全のための重要な機能でもあります。
不要なトラブルを避けるためにも、キーフォブの状態やセキュリティ設定を定期的に確認しておくことが大切です。
バイクのエンジン警告灯は何種類?

バイクのエンジン警告灯は、大きく分けて「赤」「オレンジ(または黄色)」「緑」の3種類があります。
それぞれの色には異なる意味があり、トラブルの緊急度や必要な対応も大きく変わります。
まず赤色の警告灯は、即座に対処が必要な「重大な異常」を示します。
例えば、オイルの油圧低下や冷却水の異常温度など、放置するとエンジンが故障するレベルのトラブルが対象です。
これが点灯したまま走行を続けると、エンジンの焼き付きや車両火災のリスクが高まります。
次に、オレンジや黄色の警告灯は、エンジン制御や電装系統など「早めの点検が必要な異常」を知らせるものです。
チェックエンジンランプやABSの異常通知などがこの色に該当します。
走行自体は可能な場合もありますが、症状が悪化する前に原因を突き止めたほうが安心です。
一方、緑色の警告灯は異常を示すものではありません。
これは「作動中の状態」を表示するインジケーターであり、ニュートラルランプやウインカー作動の表示などが該当します。
運転操作を補助するための表示なので、基本的にトラブルではありません。
ただし、点灯している色だけでなく、点滅のパターンや点灯するタイミングも判断の重要な材料になります。
例えば、エンジン始動時に一瞬点灯するのは自己診断の一環であり、異常ではありません。
このように、バイクのエンジン警告灯には複数の種類があり、それぞれが伝えるメッセージには明確な違いがあります。
色や状態を正しく見極めることで、より安全でトラブルの少ないバイクライフを送ることができます。
ハーレーの警告灯一覧とトラブル対処法
- エンジンチェックランプが点いたり消えたりする原因
- エラーコードの見方と確認の手順
- エラーコード「p1608」の意味と対処法
- オーバーヒートで警告灯が点灯した場合の対応
- 警告灯がついたまま走行してもいい?
- 警告灯の消し方と正しいリセット方法
- トラブルコードの消し方は?
エンジンチェックランプが点いたり消えたりする原因

エンジンチェックランプが点いたり消えたりする場合、一時的な異常が原因であるケースが多く見られます。
常時点灯している状態とは異なり、断続的な点灯はその場限りのエラーや軽微な不具合の可能性があるため、慎重に見極めることが重要です。
このような状態になる背景には、主に以下のような要因が考えられます。
- センサーの一時的な誤作動
例えば、O2センサーや吸気温度センサーが走行中の振動や気温の変化によって一瞬だけ異常値を出すと、ランプが一時的に点灯することがあります。
正常値に戻ると、ECM(エンジンコントロールモジュール)が自動的にランプを消灯させるため、ドライバーは「点いたり消えたり」という状態を目にします。
- 過去に発生したエラーの履歴が残っているケース
すでに不具合自体は解消されていても、ECMの内部には記録が保持されており、その履歴が原因で一時的にランプが反応することがあります。
これは一定の走行サイクルが経過するまで消えないこともあります。
- バッテリーの電圧が不安定な場合
特に寒冷時や、バッテリーの寿命が近いときに見られがちな症状です。電圧が正常に戻ればランプは自然に消える場合がありますが、繰り返し発生するようであれば注意が必要です。
- 社外パーツによる影響
マフラーやエアクリーナーを純正以外に交換していると、燃調のバランスが崩れて誤検知が発生することがあります。FUELPAKなどの燃料調整デバイスを使用している場合には特に注意が求められます。
このように、点いたり消えたりするエンジンチェックランプは必ずしも故障とは限りませんが、異常の兆候である可能性も否定できません。
自己診断モードでエラーコードを確認するか、念のため整備工場で診断を受けるのが安心です。
エラーコードの見方と確認の手順

ハーレーのエラーコードを自分で確認できるようになると、トラブルの原因を素早く把握しやすくなります。
専門機器がなくても、車両本体だけでチェックできるため、ライダーにとっては非常に便利な機能です。
まず行うのは「自己診断モード」の起動です。
これは車両のメーターに搭載されている診断機能で、特別な工具は不要です。
具体的な操作手順は以下のとおりです。
- イグニッションをオフにして、キルスイッチを「RUN」にセットします。
- トリップオドメーターのボタンを押し続けたまま、キーをイグニッションポジションまで回します。
- メーターに「diag」または「dlAg」のような文字が表示されたら、ボタンを離します。
- 再度トリップボタンを押すことで、診断対象モジュール(例:P、S、SP、t、b)を順番に切り替えられます。
各モジュールにはそれぞれ以下の意味があります。
- P:パワートレイン(エンジン制御関連)
- S:セキュリティモジュール
- SP:スピードメーター関連
- t:タコメーター
- b:ブレーキ(ABSなど)
調べたいモジュールが点滅している状態で、トリップボタンを5秒間長押しすると、エラーコードが表示されます。
コードの例としては「P0134」「U1301」などがあり、頭文字によって分類が異なります。
- P:エンジンや燃料系統
- U:通信系統(シリアルデータなど)
- B:ボディ(照明やアクセサリー)
- C:シャシー(ABSなど)
エラーが存在しない場合は「none」または「nonE」と表示され、トラブルがないことを意味します。
この診断機能を理解しておけば、たとえば旅先でトラブルが起きた際にも慌てずに状態を把握できるようになります。
また、ディーラーに相談する際も、具体的なコードを伝えることでスムーズにやり取りが進みます。
なお、エラーコードは一時的な異常でも記録されることがあります。
すでに解消された問題も残るため、点灯タイミングや症状の有無とあわせて総合的に判断することが大切です。
エラーコード「p1608」の意味と対処法

エラーコード「P1608」が表示された場合、それはハーレーの電源系統、特にバッテリー電圧に関する異常を示しています。
これは珍しいコードではなく、ライダーが自分で対処できるケースも少なくありません。
このコードの主な意味は、ECM(エンジンコントロールモジュール)が「電力供給が不安定だった」という履歴を記録したということです。
よくある原因としては、以下のようなケースが考えられます。
- バッテリーの電圧低下
長期間バイクを動かさなかった後にエンジンを始動した際や、バッテリーの寿命が近いときにこのコードが出ることがあります。
- 端子の緩み
端子の接触不良や腐食、アース線の緩みなどでも同様のエラーが記録されるため、見逃せません。
- 過去に発生したバッテリー上がりの履歴
過去にバッテリー上がりが発生していると、車両のECMにその履歴が記録され、エラーコードP1608として表示されることがあります。
対処法としては、まずテスターでバッテリーの電圧を測定し、12.5V〜13.0Vを下回っていないか確認します。
基準値を下回っている場合は、充電またはバッテリーの交換が必要です。そのうえで、端子がしっかり固定されているか、腐食がないかも確認しておくと安心です。
問題がなさそうであれば、「P1608」は過去の履歴として残っているだけの可能性もあります。
この場合は自己診断モードでエラーコードを表示させたあと、トリップボタンを長押しして「CLEAr」の表示を確認すれば、リセットが完了します。
ただし、リセット後に再び同じエラーが出る場合は、原因が継続中である可能性が高いため、無理に走行せずディーラーで診断を受けるのが賢明です。
このように、「P1608」は致命的なトラブルではない場合が多いものの、電装系統のトラブルを早期に知らせてくれる重要なサインです。
放置せず、点検と判断を早めに行うことで、安心してバイクに乗ることができます。
オーバーヒートで警告灯が点灯した場合の対応

ハーレーでオーバーヒートの警告灯が点灯したときは、冷却が追いついておらず、エンジン温度が安全範囲を超えている状態です。
このまま走行を続けると、エンジン内部に深刻な損傷が発生する恐れがあるため、できる限り早く対応する必要があります。
まずは、交通状況を見ながら安全な場所に停車しましょう。
いきなりエンジンを切るのではなく、数分間アイドリング状態を保つことで、冷却ファンやオイルによる自然冷却が機能します。
すぐに電源を落としてしまうと、エンジン内に熱がこもったままになることがあるため注意が必要です。
エンジンがある程度冷えたら、以下の点をチェックしてみてください。
- 冷却水の残量(ツインクールドモデルの場合)
ツインクールドモデルでは、オーバーヒート防止のため冷却水の残量を定期的に確認し、不足していれば早めに補充することが重要です。
- ラジエーターや冷却ファンの動作状況
ラジエーターや冷却ファンが正常に作動していないと冷却効果が大きく低下するため、異音や作動不良がないかを走行前後に点検しましょう。
- 冷却フィンへの虫やゴミの詰まり
冷却フィンに虫やゴミが詰まると放熱効率が落ちるため、走行後などに目視で確認し、必要に応じてエアやブラシで清掃しましょう。
- エンジンオイルの量と汚れ
エンジンオイルが不足していたり汚れていたりすると冷却効果が低下するため、定期的に量と色・粘度を確認し、必要なら交換を行いましょう。
また、信号待ちや渋滞中など、風が当たりにくい状況でもオーバーヒート警告が一時的に点灯することがありますが、これが頻繁に起こるようなら点検が必要です。
さらに、冷却水の補充や点検を行う際は、エンジンが完全に冷えてから作業をしてください。
高温状態でキャップを開けると、蒸気や熱湯が吹き出し、大きなやけどにつながる恐れがあります。
このような対応をしても再び警告灯が点灯するようであれば、冷却系センサーやサーモスタットの故障も考えられます。
自分で解決が難しい場合は、無理に走らずディーラーや整備工場で詳しい点検を受けることが安全です。
エンジンのオーバーヒートは、車両からの「異常を知らせる最終サイン」とも言えます。
冷却を最優先に対応することで、大きな損傷を未然に防ぐことができます。
警告灯がついたまま走行してもいい?

警告灯がついたままの状態で走行するのは、安全面や車両の寿命を考えると推奨できません。
とくに赤やオレンジの警告灯は、重大な異常や故障の予兆を示していることが多く、無理に運転を続けると状況が悪化するリスクがあります。
まず警告灯の「色」に注目してください。
赤いランプは、エンジンやオイル、冷却系など、生命線ともいえる部分の異常を示しています。
このまま走行するとエンジンの焼き付きやブレーキ機能の低下など、致命的なトラブルにつながるおそれがあります。
速やかに停車し、状態を確認することが必要です。
一方で、オレンジや黄色の警告灯は、今すぐ停止するほどではないにせよ、早期点検が必要な問題を知らせています。
たとえば、ABSが機能していない、センサーに異常がある、燃調が崩れているといったケースです。
走行は可能でも、制動力や燃費に悪影響を与える可能性があるため、無視はできません。
ただし、緑のランプがついている場合は、ほとんどが正常な作動状態を示すインジケーターです。
ニュートラルランプやウインカー表示などが該当し、異常とは無関係です。
ここで注意したいのは、点灯の原因がすぐに判別できないことも多いという点です。
外見上は問題がなさそうでも、内部のセンサーが異常を検出している可能性もあります。
もし走行中に警告灯がつきっぱなしになったら、なるべく早く安全な場所に停車し、エラーコードの確認やディーラーでの点検を検討してください。
このように、警告灯が点灯したままでも走れるケースはありますが、走ってよいかどうかは「何色の警告灯が、どのような状況で点灯しているか」によって判断が分かれます。
自己判断に頼りすぎず、必要な場合は専門機関に相談するのが最善の対応です。
警告灯の消し方と正しいリセット方法

警告灯を消すには、まずその点灯原因を把握し、必要な対処を終えたあとで適切なリセット操作を行う必要があります。
原因が解消されていない状態でリセットしても、すぐに再点灯するため意味がありません。
ハーレーの多くのモデルでは、「自己診断モード(ディアグノーシスモード)」を使ってエラーコードを確認し、必要に応じて手動でリセットできます。
この機能を活用すれば、バイクショップに持ち込まずとも警告灯を消すことが可能です。
操作手順は以下のようになります。
- イグニッションをオフにし、キルスイッチを「RUN」の状態にします。
- トリップメーターのスイッチを押しながら、キーをイグニッションポジションまで回します。
- 液晶画面に「diag」や「PSSPt」などの表示が出たら、ボタンを離します。
- トリップボタンを1回ずつ押すと、「P」「S」「SP」「t」「b」などの診断モジュールが切り替わります。
- 消したいエラーが記録されたモジュールが点滅している状態で、ボタンを5秒以上長押しします。
すると、エラーコードが表示されます。その状態で再びボタンを5秒以上押し続けると、「CLEAr」の文字が表示され、リセットが完了します。
なお、警告灯の中には自動で消えるものもあります。
たとえば、燃料残量警告灯や冷却水不足の表示などは、必要な補充を行えば自動的に消灯します。
その一方で、エンジンチェックランプなどは、原因がなくなっても履歴が残るため、手動リセットが必要になる場合があります。
また、応急的な方法として「バッテリーのマイナス端子を外して電源をリセットする」という手段もありますが、これには注意が必要です。
この方法では時計やトリップメーターなどの設定も初期化されるほか、一部のエラーは再点灯することもあります。
警告灯は単に消すことが目的ではなく、「何の異常を知らせていたのか」を理解したうえで、根本的な解決を図ることが大切です。
必要に応じてディーラーでの診断を受けることも、確実な対応のひとつです。
トラブルコードの消し方は?

ハーレーに表示されるトラブルコード(エラーコード)は、異常が発生したときに車両が自動で記録する情報です。
問題がすでに解決していても、コードだけが残っている場合があるため、必要に応じて消去することでメーター表示や警告灯をリセットできます。
トラブルコードの消去には、車載メーターを使った「自己診断モード」でのリセット操作が一般的です。
次の手順に従って操作してください。
- イグニッションをオフにし、キルスイッチを「RUN」の状態にします。
- メーター横のトリップボタンを押したまま、キーをイグニッションポジションに回します。
- 液晶画面に「dlAg」や「diag」と表示されたら、トリップボタンを離します。
- 表示が「P」「S」「SP」「t」「b」などの診断モードに切り替わるので、消去したいモジュールを選びます(点滅状態で選択)。
- トリップボタンを5秒間長押しすると、該当モジュールのトラブルコードが表示されます。
- 再度5秒以上長押しすると、「CLEAr」の表示が出て消去されます。
この方法は、すでに修理が終わっている、もしくは一時的な不具合だったトラブルコードの消去に有効です。
ただし、原因が解決していないまま消去を試みても、再度コードが記録されてしまうため、まずは異常箇所の確認を優先しましょう。
また、年式やモデルによってはタコメーターやABSが搭載されていない車両もあり、特定のモジュールが「no rSP(応答なし)」と表示されることがあります。
これは故障ではなく、単にその機能が存在しないことを示しているだけです。
一部のユーザーは、バッテリー端子を外して電装系を初期化する方法を試すこともありますが、このやり方では全ての記録がクリアになるとは限らず、設定の再入力が必要になるケースもあります。
トラブルコードの消去は、症状が解決してから行うのが基本です。
原因が明確でない場合や、何度も同じコードが出るときは、無理にリセットせず、整備工場での診断を受けることが安心につながります。
ハーレーの警告灯一覧の意味と正しい対処法まとめ
- 赤の警告灯は重大な異常を知らせる最も危険なサイン
- オレンジの警告灯は早期点検が必要なトラブルを示す
- 緑の警告灯は正常な作動状態を表すインジケーター
- 鍵マークの警告灯はセキュリティ関連の異常を示す
- エンジンチェックランプの点滅は一時的な異常の可能性がある
- バイクの警告灯は色ごとに意味と緊急度が異なる
- オーバーヒート警告は冷却系トラブルや油量不足が原因になる
- エラーコード「P1608」は電圧低下や電源トラブルの履歴を示す
- エラーコードは自己診断モードで確認・消去が可能
- 自己診断モードではメーター操作だけで異常を確認できる
- 赤色警告灯の点灯中は走行を中止するのが基本
- ABS異常時は制動距離が長くなりスリップリスクが高まる
- 緑のランプが常時点灯する場合はスイッチや配線の異常も疑う
- バッテリーの劣化や電圧不安定もエラーコードの原因になる
- トラブルコードのリセットは異常解消後に行うべきである